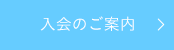大藤信郎『くじら』『幽霊船』デジタル復元について
デジタル化の経緯
日本アニメの先駆者・大藤信郎(1900-1961)の代表的アニメーション作品『くじら』『幽霊船』の2作品が今春デジタル復元され、先ごろ、東京国際映画祭(10月19日・六本木シネマート)において公開された。
遡ること1年3ヶ月前、平成24年6月、東京国立近代美術館フィルムセンターより、 当連盟が著作権を管理する大藤信郎の『くじら』『幽霊船』の2作品をデジタル復元したいとの申し出があり、デジタル復元に向けて動き出した。
当連盟が著作権を管理する大藤信郎の『くじら』『幽霊船』の2作品をデジタル復元したいとの申し出があり、デジタル復元に向けて動き出した。
デジタル復元にあたっては、デジタル化と併せて、保存とその活用もテーマとし、500年の保存に耐え得ると言われる、富士フイルムが開発した青、緑、赤の三色に分解して白黒銀画像としてフィルム(ETERNA-RDS 米国アカデミー賞科学技術賞受賞)に変換する方法を採用。1950年代初期カラーフィルムのアニメーション作品がどのような色彩で再現されるか。また、北米以外ではあまり行われていない三色分解による映像資産の保存など話題性も高く、多くの注目が集まった。
フィルム作品のデジタル修復・復元について、これまで、短編・長編映画『羅生門』『新・平家物語』『忠次旅日記』などで20作品ほどあるが、戦後初期短編カラーフィルムのデジタル復元は珍しい事例であると言える。

日本のアニメーションの先駆者・大藤信郎は、1900年東京・浅草で生まれた。大藤は25歳のとき『馬具田城の盗賊』(1926)でデビューし、以後、千代紙映画社を中心に着実に作品を発表し続け、1961年に没するまでに約50作品を残した。
特に戦後製作された『くじら』(1953)は、色セロファンによるカラー影絵アニメーションで、1953年にカンヌ国際映画祭に出品されると、惜しくもグランプリは逃したものの、ピカソやコクトーから絶賛されるなど、高い評価を受けた。続く、『幽霊船』(1956)も、ヴェネチア国際映画祭で特別賞を受賞し、大藤は世界的に脚光を浴びた。
大藤信郎が1961年に没すると、「毎日映画コンクール」(主催:毎日新聞社)では、翌年より「大藤信郎賞」を設け、主に実験的なアニメーション映画に対して賞を贈り、数々の世界的なアニメーターを輩出してきた。
大藤のアニメ手法について
1924年、大藤は“千代紙映画”という特殊なアニメーション映画を作った。それは、背景に日本特有の千代紙を使用したもので、まずは千代紙を切り抜き、奥行きを感じさせるために、重ねられた数枚のガラス板の間にはさむ。同じく、千代紙でできた人間や動物の絵も配置し、少しずつ動かしつつ1コマずつ撮影するものであった。

例えば、アマチュアの映画作家・荻野茂二が制作した記録映画『色彩漫画の出来る迄』(1937)(DVD『大藤信郎 孤高の天才』に収録)には、大藤自身が出演し、『カツラ姫』を作る工程が描かれており、その作品からも知ることができる。
1927年、ドイツ式の影絵の手法に不満だった大藤は、ドイツ式と全身を動かす方式を併用した新しい手法を考案し、『鯨』を撮影した。このアニメーション映画は、影絵によるアニメーション映画としては、日本初の作品で、翌年(1928)、日本の劇映画『十字路』とともにフランス人の買い手に販売された。
戦後、大藤は『蜘蛛の糸』(1946)という、新しいジャンルのアニメーション映画を製作し、この映画はウルグアイで開催された日本映画祭で発表される。
その後、大藤は、新しい手法を考案。それは、映画作りに“色セロファン”を使用するもので、この技法で先の『鯨』を作りなおし、この作品『くじら』が1953年、カンヌ映画祭で紹介されることになったのである。
デジタル復元の工程について
デジタル復元のおおよその作業工程としては、まず、現存する素材から復元もととなる素材を確定し、それから「スキャニング用フィルム」を複製。ローデータとして「LTOテープ」に保存。修復作業を行い、「デジタルソースマスター」を作成。そのマスターから、三色分解用35㎜インターメディエイトネガを作成。そのネガより35㎜プリントを作るというものである。
映文連で著作権を預かる大藤信郎の『くじら』『幽霊船』のフィルムは、㈱東京現像所に保管されていたが、デジタル復元作業はIMAGICAで行われるため、IMAGICAへ移されることになった。

『くじら』(1953年公開)のオリジナル素材は、映文連所蔵のさくら天然色カラー(ポジ・ポジ法)による35ミリデュープネガ(1963年)とサウンドネガ。
『幽霊船』(1956年公開)は、フジカラー(ネガ・ポジ法)による、35ミリオリジナルネガ(1956年)とサウンドネガ、35ミリマスターポジ(1969年)等であった。
これらと東京国立近代美術館フィルムセンターが所蔵している『くじら』の16ミリさくらカラーリバーサル(公開当時か)、16ミリカラープリント(1969年)、『幽霊船』16ミリカラープリント(年不詳)、映文連のネガより作成したプリント(2004年)等の検証が行われた。その結果、『くじら』は35ミリデュープネガ(1963年)、『幽霊船』は35ミリマスターポジ(1969年)を元素材としてデジタル復元を行うのが最適と判断された。
まず、フィルムセンター、デジタル復元作業を行うIMAGICAのチームと映文連の三者で打合せを持ち、作業工程などについて話し合った。さらに三色分解工程の技術的な確認を行った。
12月、いよいよ復元作業に入ることになり、12月11日にフィルムセンター担当者立会いのもと、IMAGICAのスタジオでテレシネをしたフィルム状態の現状確認と色味のチェックが行われた。
年が明けて、1月9日に取り込んだ作品のカラーグレーディング作業が行われた。各作品の問題箇所をチェックし、どのような方針で復元を行うか検討、修復はできるだけ当時に近い形で行われることになった。元素材から取り込んだ映像の色彩はかなり美しく、非常に良い形で復元が完成する見通しとなった。
1月18日に作品のフリッカー除去をどういう方針で行うか確認。2月6日には、キズパラ消しの状態をチェックし、デジタルソースマスター作成への最終確認を行った。
2月14日に音声確認をして、3月に入り、大阪のイマジカウエストにてフィルム関係の最終作業を行った。3月19日に初号試写、その後、先付け・クレジット確認などを経て、3月29日にデジタル復元作品は無事完成した。
復元のポイントについて
作品には、様々な特徴がある。作者がすでに存命しておらず、その作品の制作過程を知る人はいない今日となっては、残されたフィルムを検証し、専門家の意見を聞きながら、作家の他の作品や撮影素材(大藤の場合はセロファン)を参考により良い復元を行うしかない。
復元のポイントは、戦後まもなくのフィルムである『くじら』は退色が進んでおり、「色彩をどこまで再現できるか」であり、また「オリジナルに含まれる“瑕疵”の修復をどうするか」という点もあった。フィルムセンターのデジタル復元の方針は、オリジナルを尊重し、できるだけ封切り当時のバージョンに回復していくこと。
作品の細部に渡って検証が行われたが、例えば、『YUUREI SEN』には、黒コマがあり、ネガに黒コマを入れて、黒コマのある状態で繋いだと思われた。「それを埋めるか、前後どちらかを伸ばすか」の判断になり、「何かの意図があるのでは」という意見も出て、オリジナルネガより判断することになった。
その他、船のマークのぼけ、人物の動きの戻り、人物シルエットに背景なし、バッテン、テープ痕跡、明るさオーバーなど、小さな問題点はかなり見つかった。
また、例えば、『くじら』では、くじらの上で女が逃げるシーンに「塗りつぶし」箇所も見つかった。普通は見せてはいけないものである。『YUUREI SEN』では、船の乗り込んだ海賊(鬼)が女を追いかけるシーンでは、途中で人物のレイヤーが変わり、鬼の姿が大きくなる。しかし、「大藤さんがOKを出しているものは残す。判断ができないものはそのままに」のフィルムセンター側の方針で、よほどの単純な瑕疵でないかぎりはそのまま残し、大藤作品の味わいともなっている手作り的な影絵の魅力は可能な限り保持されることになった。
色の再現について
例えば、2作品を通じて、船の帆や女の腰巻きなどに赤い色が何度も出てくるため、「赤」をどう捉えるかは、大きな問題であった。
 カットによって帆の赤みが変わる。できるだけ揃えるために「イエロー」を足したりなどして、鮮やかな「赤」を出すようにした。また彩度を上げると欠点が見えるため、上げられず。『くじら』についてRGBの「G」を抜いて、コントラストをつけ、赤みのにごりを取るなどしている。結果としては、女の腰巻きの色や帆の色味もよく出た。
カットによって帆の赤みが変わる。できるだけ揃えるために「イエロー」を足したりなどして、鮮やかな「赤」を出すようにした。また彩度を上げると欠点が見えるため、上げられず。『くじら』についてRGBの「G」を抜いて、コントラストをつけ、赤みのにごりを取るなどしている。結果としては、女の腰巻きの色や帆の色味もよく出た。
海の波は、何枚もセロファンを重ね、微妙な波のグラデーションを醸し出しており、クリアな色でもなく、当時の発色は渋い雰囲気があった。にごりの部分についてよく考えて作業が行われたが、それは厳しいものであった。
また、夕方には見えないシーンがあり、黄色を強くすることは可能だが、全体に黄色を出せば、「赤」もずれてしまう。出し方が難しかったが、かなり良いところまでいくことが出来た。また「グリーン」の彩度が少し低いため、2分の1上げるデジタル的処理も行われた。緑の葉の部分もバランスをとりつつ、「グリーン」が足された。
くじらのお腹の中は真っ黒であったが、締めることは可能だが、コントラストがあり、周りが落ちていて、半絞り状態。結局、大きく手は加えなかった。
フリッカー除去について
撮影当時の光のばらつきをどこまでとるかは、一つの検討課題であった。全体か或いは部分か、つまり自動パラ消しを行うか、或いは明るさや色で切り分けて部分的に行うか。検討の結果、退色度合いが大きい『くじら』は、もともと光量のばらつきがあり、赤・黄色など色によって違うため、部分処理を行う。他方『YUUREI SEN』は全体で行うことになった。
『くじら』のタイトル出しについては、文字にスポットをあてるか、ベースにスポットをあてるかが検討された。つまり、背景合わせにするか、文字合わせにするか。検討の結果、背景を止めてトップタイトルを入れる方法でいくことになった。
また、「END」は終わり方が異なるため、映文連のオリジナルネガ版で確認することになり、結局、途中で動くが、そのまま残すことになった。これも出来るだけ、封切り当時のバージョンのままにするという方針が貫かれた。

上記のように、色彩の再現やフリッカー除去など、個々の作品についてかなり細かい調整がおこなわれ、結果として、戦後まもなくのさくら天然色カラーとフジカラーの作品としては、色がよくでて非常に鮮やかに復元された。
なお、2作品はデジタルソースマスターから青、緑、赤の三色に分解して白黒銀画像としてフィルムレコーディングする「三色分解」が行われ、これらのネガから1本のカラープリントが作成されたが、たとえば、100年後、フィルムがなくなり、ネガしか残っていなくても新たなデジタルデータが作成できるよう、フィルムにはカラーマネージメントデータが記録されている。このような試みを、後世の人がどのような判断するか、楽しみでもある。
当時の製作事情と大藤信郎の評価
さて、今回復元された2作品が誕生した1950年代のアニメーション映画の製作状況はどうであったのだろうか。
大藤は、1956年仏・カンヌで開催された国際会議で日本のアニメーションの現況報告を行っている。まず、代表的な製作者を紹介したうえで、今、日本には、日動映画㈱、千代紙・影絵映画研究所、村田漫画映画製作所、芦田漫画映画製作所の4社しかない。「現代日本では、芸術作品としての短編映画そのものに従事する会社は一つもない」と嘆いている。(註1)当時、短篇映画の製作会社は80社以上あったが、多くは広告や教育映画を手がけている。「短篇映画コンクール」と称するものも開催されているが、応募される作品は、広告や教育映画。大藤作品のような前衛映画は、そこでは「不良で異端」とされる。『くじら』は、カンヌ映画祭での発表により、高く評価されるまで全く価値のない作品とみなされていたと。
大藤は、『くじら』の制作に200万円費やしたが、収入はまったく無かった。この様な状況下では、新人の技術者を育成することは全く不可能、と現状を嘆いている。
今回、復元のプロセスで学習研究社が60年代、中学生向けに作ったスライド(文部省)『影絵映画の王様』(註2)が見つかったが、これには大藤信郎と姉・八重の物語が描かれており、その中にもこんなくだりがある。
外国では、このように認められ、有名になった大藤も、「日本ではあいかわらず日のあたらぬ道を歩いていた。短い影絵映画は、なかなか上映してくれるところがないし、テレビの動画映画を作ろうとしない信郎の生活は、いつも貧しかったのです。・・・」 当時、海外では認められても、国内ではなかなか評価されない現実があったようで、先の嘆きにつながったのではなかろうか。
しかし、『くじら』で評価されたあと、大藤も少しポピュラーになったのか、週刊読売臨時増刊号には“グランプリをねらう奇人”として紹介されている。グラビア特集が組まれ、大藤の『YUURE SEN』のカットから作品制作工程、日常生活の様子まで紹介している。「若い時は背が低いのを恥ずかしがって、ずっと家にとじこもったきりだったが、近ごろは、ときどき銀座などにも出かける。通行人の歩きかたや服装、なにからなにまで観察材料になる」とキャプション。(註3)大藤氏は趣味と実益を兼ねた踊りは師匠格で黒田節やおけさは定評があると紹介され、民踊研究会で同好者に混じって楽しそうに踊る大藤氏の写真が掲載されている。
大藤は、彼を支えた姉の八重と姪のわずか3人で制作していたと言われ、海外では高く評価されたものの、時にはアウトサイダーと見なされ、エロティシズム漂う作風のせいか、賛否両論が分かれ、日本ではほとんど評価されてこなかったとされる。(註4)
今回復元された『くじら』にも、赤い腰巻きの女を男たちが争って追い回すシーンがあるが、これらの描写に対し、「陰湿さこそあれ、耽美的な魅惑のひとかけらさえも見当たらない」(註5)と切って捨てる向きもあった。
しかし、上記週刊誌に飯沢匡氏は、色セロハンを用いた映画制作作業のたいへんさを述べたうえで「それを、まことにほがらかに、生活をたのしみつつ、やっていくのだから、やはり奇人というのだろうか。(中略)本人にあった人は全然そんな暗いかげは感じない。血色のよい顔をほころばせて、歌舞伎の見得を切って見せたり、民謡をうたってくれたりする朗らかなおじさんなのである」と書いている。(註6)
大藤は存外ほがらかな性格で製作費のやりくりに苦労はあったものの、姉の八重に支えられながら、生活を楽しみつつ、根っから好きなアニメーションを作りつづけたのではなかろうか。
大藤は、シネマスコープの大作に取りかかったところで、長い間の過労が祟ったのか、1961年7月28日仕事半ばにして亡くなる。61歳であった。
先の学研スライドが制作されたのは、1960年代後半。文部省の道徳教育の指導資料として制作されている。スライドのテーマは「わたしの考える幸福」「幸福とは」。いろいろな困難にぶつかりながらもそれに打ち勝ち、影絵映画制作に打ち込む大藤と姉の八重。姉の励まし、よりよい映画を作りたいという大藤の情熱・・・。この『影絵映画の王様』を見せて、大藤姉弟の生き方を提示し、生徒に「幸福とは」何かを考えさせたかったようだ。
さまざまな評価があるかもしれないが、このような道徳教育のテーマとして取り上げられるくらいだから、決してマイナスイメージだけで見られていたわけではないだろう。かなり肯定的に捉えられていたのではなかろうか。

大藤が亡くなった翌1962年には、「毎日コンクール」に大藤信郎賞が設けられた。第1回は手塚治虫の『ある街角の物語』に贈られ、その後、和田誠、久里洋二、川本喜八郎、岡本忠誠、宮崎 駿、山村浩二、大友克洋など、これまで数多くの日本のアニメーターやアニメーション制作会社に賞が贈られてきた。その名は継承され続けているのである。
デジタル化の進展とこれから
映画が誕生して110年余り。今、フィルム文化は、かつてないほど、大きな変化に見舞われている。映画を上映する劇場は急速にデジタル化が進み、その比率は今や85%に達していると言われ、加えて、これまで撮影用・上映用の映画フィルムを供給してきた国内大手メーカーが、35ミリフィルムの製造を平成25年3月にやめた。フィルムによる映画上映や映画製作にも大きな変化が訪れている。
映画作品の長期保存という観点からみると、テープメディア場合、一つのフォーマット媒体にデータ保管する目安は10年と言われ、デジタルメディアによる保存にも課題が浮かび上がっている。勘弁で安価なデジタル化が、映画を撮りたいと思う多くの人々に門戸を開き、映画製作を可能にしている反面、デジタル化の急速な進展は、映画作品のアーカイブにも切実な課題を投げかけている。
今回、幸運にも大藤の二作品『くじら』『幽霊船』は、500年の保存に耐え得ると言われる三色分解フィルム(ETERNA-RDS)に保存する方法でデジタル復元され、保存と活用を図られることになったが、このような短編映画は稀である。
数多くのフィルム作品はこの先どうなるのか、まして、最初からデジタルで制作された作品はどうなるのか、映画は「文化」としてこれからも受け継がれていくのか、今考えるべき時がきている。
事務局長 中嶋清美
註1:NFC NEWSLETTER 2010年8-9号 映画史文献発掘⑧
註2:<文部省中学道徳資料スライド>『影絵映画の王様−幸福−』製作㈱学習研究社)
註3:「週刊読売臨時増刊号 現代奇人怪物読本(1956年)」
註4:津堅信之『日本のアニメーション力』NTT出版
註5:森卓也『アニメーション入門』美術出版社
註6:飯沢匡「週刊読売臨時増刊号 現代奇人怪物読本(1956年)」